ハイヤー業界が熱い!?8大業界から見るハイヤーの今と今後をお届け
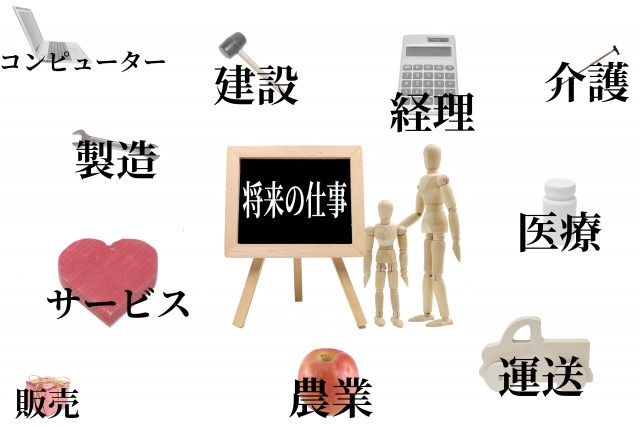
就職活動を行う上で知っておきたいポイントの1つにその業界の今後の動向が挙げられます。
そんな業界の動向としてハイヤー業界の今と動向をお届けします。
その前にまずは、仕事のジャンルを大きくわけると8つにわけることができ、これを8大業界と呼んでいます。
まずは、この8大業界を1つずつ見ていきましょう。
業界① 官公庁・公社・団体
まず、はじめに紹介するのは、唯一民間ではないジャンルにあたる『官公庁・公社・団体』業界です。
国や国立学校といったあくまで国の管理下にあるものや市役所や地方自治体といった行政サービスを提供している業界のことを指します。
警察や裁判所も大きく分類するとこの業界に割り振ることができます。
業界② 金融
お金というわかりやすく生活に溶け込んでいる業界です。
銀行やクレジット会社などがこの業界にあたるので、業界の中でも比較的想像しやすい部類にあたります。
さらに紀元前からあったとされ、等価交換の時代にも紙幣や硬貨に代わる銀行があったとされるほど歴史が古く、親しみのある業界と言えるでしょう。
また、保険会社も保険というサービスを提供しているものの金融業界にあたります。
業界③ 小売
こちらも金融同様わかりやすく生活に溶け込んでいる業界の1つで、スーパーやコンビニといったものが、小売業界にあたります。
商品の大小はもちろんその規模間に関わらず、消費者に対して商品を売るということを生業としている企業は全て小売にあたります。
そのため、百貨店とコンビニでは、1店舗あたりの規模や売上高が異なってくるにも関わらず、どちらも小売にあたるのは、表現として不適切に感じることがあるかもしれません。
ただこの小売は、消費者からの目線ではなく、「最小単位に小分けして販売する」という製造業や卸売業から見た目線からのものとなっているため、業界の1つとして小売となっているのです。
業界④ メーカー
一言にメーカーと言ってもそのジャンルは多岐にわたります。
化粧品や車の部分、食品、電子機器など、例を出すと挙げてもあげきれないほど、数多くの種類があり、まとめてメーカーと呼ばれているのが特徴です。
そのため、就職する際には、どういうメーカーなのか、同業者との差別化として何があるのかをきちんと見極めておく必要があると言えるでしょう。
業界⑤ 商社
商品の販売を支援する業界のことで、メーカー業界との関係性が深い業界です。
そんな商社は、様々な商材を取り扱う『総合商社』と特定の商材のみを取り扱う『専門商社』の大きく2種類にわけることができます。
ただ、近年では、メーカー業界自身が商社としての役割を担う企業も数多く存在してきており、1つの企業で2つの業界が混ざっていることもあり差別化が難しくなっています。
特に就活生にとっては、その企業がメーカーなのか商社なのかが、わかりづらくなってきているため、キャリアセンターに足を運んだり、企業のホームページやSNSを念入りにチェックしたりすることがより重要になってくる業界となります。
業界⑥ マスコミ・広告・出版
テレビやインターネット、SNS、書籍といった複数の媒体において、様々な情報を発信する業界です。
時代に合わせて変化することが多く、テレビがない時代は、新聞がメインであったり、インターネットが普及するとSNSやWEB上で情報を配信したりといったその時に合わせた流行を常に追いかけて行く必要があります。
自然災害での近況確認や病気の情報発信などでは、特に重要しされ、スピーディーかつ信憑性がとても大切になってくる業界となります。
業界⑦ ソフトウェア・通信
マスコミ・広告・出版業界同様こちらも時代に合わせた変化が大きく起こりうる業界です。
通信に関しては、固定電話から携帯電話、スマートフォンといったように少し前までは、想像もしていなかったものが、今では当たり前に使われているといった時代の変化をより身近に感じることができる業界です。
ソフトウェアに関しても、電気計算機の時代まで遡ると、重さ約30トンにもなるコンピューターの開発から手軽に持ち運べるように改良されたノートパソコンへと変化し、それぞれに合わせたソフトウェアの開発が行われた業界です。
AIやアプリケーションの開発もこの業界に含まれ、普段使っているものの裏側を知ることができるかもしれません。
業界⑧ サービス
最後に紹介するのが、個人や企業が求めているサービスを提供する業界で、ハイヤーも大きく分類するとこの業界にあたります。
その種類は、不動産や旅行、人材派遣、物流、美容院、飲食店といったように、メーカー同様例を挙げると数え切れないほどあります。
また、ガスや電気といったものもこのサービス業界にあたり、生活に必須になりつつあるものもこの業界には含まれています。
以上が8大業界と呼ばれる業界になります。
さらにここから細分化することで、様々な業界に行きつくことになるわけですが、冒頭でもお伝えしたとおり、ハイヤー業界がなぜ熱いのかをお届けします。
ハイヤーが熱い理由① 観光客の増加
世界規模で問題となったコロナウィルスの終息に伴い、観光業が復興しつつあり、国内旅行の増加はもちろんのこと多くの外
国人観光客が来日しています。
観光する人が増えるということは、飛行機の利用が必然的に増えてきます。
特に外国から日本に来るとなると船よりも飛行機での利用が多い傾向にあるため、空港送迎の機会が増えることになります。
また、旅先でゆったりと過ごしたい方には、バスやタクシーよりも、ハイヤーを利用した観光地巡りが選ばれている傾向にあるため需要が増加しています。
ハイヤーが熱い理由② ドライバーの少なさ
観光客が増加し、ハイヤーの利用が増えるとなると、業界側の課題となってくるのが、ドライバーの確保です。
お客様からの依頼が多数あっても送迎できるドライバーがいないことには、サービスを成り立たせることが難しいため、一定のドライバー確保は必須条件となっています。
しかしながら、ハイヤードライバーの人数は、有り余っていると言えるほどではなく、むしろ少ないです。
そのため、求人数が多く、企業によっては、免許取得のサポートまでしてくれるところまであるほどドライバー確保に勤しんでいます。
そのため、今仕事を探している方やこれから就職をする方にとっては、入りやすい業界となっています。
ハイヤーが熱い理由③ 廃止されにくい職業であること
時代の変化に伴い、職業は変化し、その時代に合わせて新しく生まれたり、無くなったりします。
わかりやすいのがソフトウェア・通信業界で、コンピューターがない時代には、ネット通販やサーバー管理という職業そのものがありませんでしたが、コンピューターの誕生に伴いこれらの職業が生まれ、今なお続いています。
逆にワードプロセッサ操作員、預貯金集金人といった職業は、ワープロの需要がなくなる、ATMの普及やコンビニでの支払いが可能になったことで、廃止された職業です。
このように廃止される職業がある中、ハイヤーは、廃止されにくい職業であると言えます。
ハイヤーも車の誕生とともに、生まれた職業ではありますが、車に代わる新しい乗り物が生まれ普及しない限り、完全な廃止が見込まれにくいです。
仮に新しい乗り物が、生まれた際には、その乗り物に合わせたドライバーとして活躍する可能性を秘めています。
また、IT技術が進み、自動運転が普及し始めているものの、全ての道を自動運転が可能にしているわけではありません。
渋滞や工事状況に合わせた迂回ルートの探索、もしもの事故に合わせた対応などは、自動運転技術ではまだ改善できておらず、人がいないことには対応が難しいとされています。
さらにハイヤーの良さとされるドライバーの接客を楽しみにしてくださっている層にとっては、人が運転することに意味があると言え、廃止が見込まれにくいことでしょう。
そのため、今後も一定の需要を確保することができるため、安定した職業の1つと言えるでしょう。
以上3点がハイヤー業界の熱い理由です。
これからドライバーを目指す方はもちろん仕事を探している、転職を考えている方にオススメできる職業になっています。
インバウンドの増加に伴い、更なる活躍を期待できるため、あなたもハイヤー業界に飛び込んでみてはいかがでしょうか?

